

 |
 |
 |
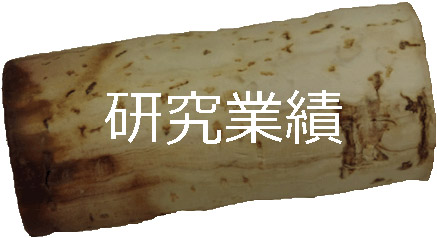 |
 |
| ◆2022年のでき事◆ |
|
3月 11日 日本食品科学工学会 関東支部大会で学会発表してきました 4年生の学生さんが令和5年 日本食品科学工学会 関東支部大会(実践女子大学)で学会発表をしてきました。卒論発表が終わり、みんな春休みを満喫…するところを、研究室にきて黙々とポスター作りを頑張っていました。ポスター原稿も印刷直前まで修正をかけて、すみませんでした!発表会場では、自ら声をかけて説明したりと初めての経験なのに関心しました。コアタイムでは、閑古鳥が鳴くこともなく、常に人が来ていたので安心して見ていられました。自画自賛ですが、ポスターも会場で1番、見やすかったと思います!同じく学会に参加されていた元食品製造学研究室教授の谷本先生にもお会いし、一緒に写真を撮りました。学生はオンラインでしか谷本先生の授業を受けていなかったので、初めて生の谷本先生と楽しく会話をしていました。この学会は、発表した学生には、協賛している食品会社さんからお土産がもらえます。しばらく、対面開催がなかったせいか…今年の大会は、お土産がモリモリです。お疲れ様でした!
| 3月 1日 引継ぎ作業中 研究室に所属予定の3年生が先輩から引継ぎ作業をうけています。
| 2月 9日 卒論発表会当日! 卒論発表です。1年間の研究成果を発表します!みんな直前まであきらめずに頑張りました!発表する本人はもちろんだと思いますが、助教も、発表が始まるとドキドキ、質疑応答が終わるとほっとしました。」と思いました。ような気分発表を終えて帰ったら修士の先輩から子供(4年生)にサプライズ!ハイハインを配られた学生もいますね。うちの研究室には子供だけでなく赤ちゃんもいるようです。
| 2月 7日 卒論発表会前日! 明日は4年生の番です。直前まで、必死に発表スライドを修正しています!発酵微生物工学研の乙黒先生から激励いただきました。
| 2月 6日 修士論文発表会 修論発表です。2年間の研究成果を発表します!
| 1月 27日 卒論・修論に向けて追い込み 卒論・修論発表に向けて追い込みです。修士は同時に修士論文も仕上げなければならいので、休日返上で練習をしていました。
| 1月 20日 研究報告会 山梨大学男女共同参画推進室主催の研究報告会・交流会がありました。博士課程の学生さんと助教が参加してきました。久しぶりの対面での場にでて、直接話せる機会はいいな(違うな)と思いました。
| 1月 11日 研究風景・ワインの味に関する研究 卒論のテーマとしてワインの味について研究している学生さん。官能評価(ヒトを分析機器としてつかう評価)の最終実験を実施中。お互いが忙しい中、みんなに協力いただき実験を進めています!研究室の仲間意識には本当に助かります!これからもこんな雰囲気が続いていければと思います。そして、みんな大詰め!頑張ろう
| 12月 28日 農場の冬景色 用事があって農場に行ってきました。夏場(収穫シーズン)は行かせてもらいますが、そういえば冬はほとんど来たことがない。ブドウの木がキレイに選定されていて、いよいよ冬という風景でした。ブドウの木を管理していただいて感謝です。
| 12月 19日 研究風景・ワインの味に関する研究 卒論のテーマとしてワインの味について研究している学生さんがいます。官能評価(ヒトを分析機器としてつかう評価)が中心の内容です。コロナも影響し、とても苦労していますが、いよいよ追い込み時期です。最終実験につかうワインを必死で選抜中です。
| 12月 15日 研究風景・最新のマイクロスコープ 実験データとして、微生物膜をうまく撮りたいと、岸本准教授に相談したところ、マイクロスコープが使えるのでは という提案をうけ早速キーエンスの方にきていただきました。かなり旧式のマイクロスコープがエクステンション部門に保管されているので、こちらの機器の状態をみていただいたのですが、ひらりと毛氈を敷き、最新型を出してデモンストレーションもして下さいました。最新型を見てしまうと、画素数の違いに驚かされました。そして、機器の価格にも驚きすぎて笑いしかでませんでした。目的とする微生物膜がマイクロスコープで観察できることがわかったので、あとはお金をやりくりするか?旧型でうまくやりくりする方法を考えるかの2択です。キーエンスの方には「是非、年末ジャンボを…」と言われましたが、チキンな助教は旧型でどうにか撮影する手段を考えたいと思います。
| 12月 8日 研究風景・成分抽出 当研究部門では、ブドウやワイン中に含まれる成分の機能性について研究しています。研究では、成分の抽出操作やさらに各種クロマトグラフィーなどを使って成分を分離する操作を行っています。学生さんはとある活性成分を明らかにするために、日々、格闘しております。地道な作業だけに忍耐力も必要です。毎日頑張っている姿に尊敬の念を抱きます。
| 11月 26日 日本ブドウ・ワイン学会 受賞 11月 26日 日本ブドウ・ワイン学会が開催されました。一般講演はオンデマンド形式で、特別講演等は対面での実施になりました。機能成分学研究部門に配属の学生は必須で、大会運営のお手伝いです。特別講演ではTom Collins先生によるテイスティングをいれた講演会が行われたので、その準備のためのグラス準備も行いました。思い荷物を一生懸命ワイン研から運搬中・・・。 本年度の学会賞として奥田教授が功労賞を受賞されました。長きにわたる学会の発展、普及、啓発への貢献に納得の受賞です。 また、当研究室の修士2名が大会発表賞として同点受賞致しました。 平田 佳佑 「pH がマスカット・べーリーA ワインのポリフェノールに 及ぼす影響」 受賞内容:温暖化によりワインのpHが上昇する中で,発酵前・発酵後のpH調整によりワインの品質を改善できる可能性を示しました。 受賞コメント:この度、2022年日本ブドウ・ワイン学会大会にて、名誉ある大会発表賞(口頭発表部門)をいただきました。ご指導を賜りました先生方をはじめ、サポートいただいた研究室の仲間達そして大会関係者の皆様に心より感謝申し上げます。この賞を励みに今後もより一層精進して参ります。 芹澤 樹(写真左側) 「ジグルコシド系アントシアニンは高 pH で容易に退色する」 受賞内容:近年耐病性の観点から世界的に利用が増えている非ビニフェラ系ブドウの多くに含まれるアントシアニンの赤色は,pHによって大きな影響を受けることを明らかにしました。 受賞コメント:ご指導頂きました奥田教授を始め、研究室の皆様に心より感謝申し上げます。残り少ない大学院生活ですが、悔いの残らぬよう時間を大切に使っていきたいと思います。
| 10月 31日 ハロウィン その2 ハロウィンですね。3年生の学生実験から戻ると、研究室に恐竜がいました
| 10月 31日 ハロウィン その1 3年生の学生実験が始まりました。コロナ対策で学生実験室とワイン研の研究室2か所で実施しています。修士1年生がティーチングアシスタントをしてくれています。反応はいかがでしょうか?
| 9月 29日 新しい学科パンフレット 今年度、広報を仰せつかっている関係で、学科のパンフレットを新しく作らせてもらいました。表紙右の農業男子は研究室の修士1年生です。卒業生からのメッセージ部分には研究室の卒業生に協力してもらいました。その他の卒業生の方々にも色々とお願いしてばかりですが、皆さん快く協力していただけるので感謝感謝でございます。
| 9月 5日 収穫の様子・小曲農場シャルドネ いよいよ収穫と仕込みシーズンが始まりました。醸造実験を計画している学生は勝負の時期です。うちの研究室でも醸造実験用のシャルドネを収穫しに行きました。この日はワイン研共通仕込みシャルドネ担当の発酵微生物工学研と共同での収穫作業でした。大勢学生が集まったので選果も丁寧に行いました。
| 7月 25日 研究の様子・ヤマブドウ系ワインについて 機能成分学研究室では、教員から提案したテーマ以外にも、学生自らが考えて研究テーマを設定する場合もあります。今年度はヤマブドウ系ワインの研究がしたい!という学生さんがおり、ワインを集めて分析作業をおこなっております。
| 7月 19日 研究の様子・官能評価 現在、白ワインの味を評価する…というテーマで研究を行っています。今日は、味をどのような言葉で表現できるか、言葉だしをしました。さらに、言葉を分類したり統合したりというような作業もしました。人により感じ方が違うので、そのすり合わせや意見交換は非常に重要です。活発に意見がでるので、とてもありがたいです。
| 7月 7日 星に願いを! お隣研究室のはからい?で今年も研究所玄関に笹が用意されました!短冊まで配ってくれてありがとうございます。みんなそれぞれ願い事を書いて飾りました。私も、切実な願いを書かせていただきました。どうかどうか叶いますように。できれば優先順位高めでお願いします。
| 7月 1日 OBがきたよ! 当研究室卒業のOBがきました。卒業しても後輩を気遣ってくれる先輩に感謝です。ちなみに就職先でも先輩後輩の関係が続く学生もいます。頼れる先輩がいると心強いですね。本日は、独自開発したワイン評価用のアプリについて検討しにきたそうです。しかも趣味でアプリを作るとか、私には未知の世界ですが…。アプリ完成が楽しみです!
| 6月 28日 研究の様子・菌数測定 微生物の部屋ではありませんが、評価系で微生物試験を行っているのでその一環で酵母の菌数測定をしました。トーマ血球計算盤を使用する測定は、かれこれ10年前にやったきりで記憶がうっすら。学生は3年生の実験でやっているので記憶が新しいです。といっても、もう一度、微生物部屋の先生に御指南いただけることになりました。そうそう、そうだったと思い起しながらの作業です。
| 6月 18日 OBがきたよ! 当研究室卒業のOBがきました。目的は秘密ですが、3名ともワイン業界で頑張っている方々です。後方、左からシンワフーズケミカル(株)、サンサンワイナリー、紫藝醸造さんで活躍されています。休日に研究室にいた後輩たちと記念撮影しました。
| 6月 18日 社会人向け実習 山梨大学ワイン科学研究センターで実施している山梨大学ワイン・フロンティアリーダー養成プログラムの実習を行いました。これまで担当実習では、主にポリフェノール化合物の定量やワインの色への影響などを見ていましたが、今年度は内容を変えてワインの酸に関わる成分の分析(pH、滴定酸度、有機酸組成分析、カリウム定量)を行いました。pHや滴定酸度はワイナリーさんでも行っていると思いますが、有機酸分析やカリウム定量はやっていないと思います。しかしながら、これら成分はワインのpHを左右する重要なファクターであると考え、今回の実習に組み込みました。まずは正確な分析の基本として、ピペット操作、ビュレット操作に四苦八苦しながら、実習をこなしていただきました。最後に分析値から何が読み取れるかを皆さんに考えていただきました。ここが難しいのですが。皆様お疲れさまでした。
| 6月 16日 研究の様子・カリウム定量の練習 4月から4年生は各自の実験テーマを与えられていますが、まだまだ実験の練習段階であります。今日は原子吸光光度計でカリウム濃度を測定する練習をしています。原子吸光光度計の使い方もさることながら、試料の処理や試薬調製も覚えたり考えたりする必要があります。どうやら検量線用のカリウム溶液調製で困っているようです。100 mg/L カリウム濃度( 0.5 M 硝酸溶液に溶解したもの)があるので、これを希釈して0、2、4、6、8 mg/Lカリウム濃度にして下さい。ただし、硝酸濃度はすべて0.1 Mになるようにしてください・・・の部分です。カリウムだけでなく硝酸濃度も考慮して希釈操作を行う必要があります。また、なるべく試薬を無駄にしないように、必要最低限に抑えるにはどうするのか?も考えなければいけません。頑張ってやり方を導きだしてください
| 6月 13日 出前講義をしてきました 高校で出前講義をしてきました。今回はワインの機能性成分について・・・ということでしたので、ポリフェノール化合物について話をしてきました。午後一なので、眠くなるだろうとおもい、前半は簡単な実験をしました。とても簡単な内容ですが、pHによる色の変化や、ポリフェノールの酵素的酸化と亜硫酸による酸化防止、FC法によるポリフェノール定量です。後半は、その結果を合わせながらポリフェノールについて話をしてきました。70分の短い時間でしたが、少しでも高校生の興味がひければ良かったのですが、反応は…。100%眠くならない授業をするのは難しいなと痛感しました。
| 6月 6日 1年生基礎ゼミに協力 1年生の基礎ゼミでは自由テーマでグループ研究を行います。とある班がワインの産地による違いを調べており、その中で味の違いを調べたいと協力要請がありました(1年生は飲めないので先輩にテイスティングを依頼)。どのような官能評価をするかディスカッションした結果、造りての意図する味(ラベルに書かれた味の表現)と実際に飲んだ人で答えがマッチするか?という、なかなか面白い評価をすることにしました。これがすごく難しいんですね。1年生に見守られながらのテイスティングはすごく緊張。最後は答え合わせをして、もう一度テイスティングして確認していました。先輩のプライドですね。
| 5月 31日 香りの勉強 ワインでは香りを様々な言葉で表現します。その中でゼラニウム様ってどんな香り?となったので、ハーブ園にいってゼラニウムを買ってきました(以前、自宅に植えていたのが工事で耕されてしまったので)。今回は、2種類のゼラニウム。あと白い花と表現されそうな香りの強いものもあったので購入してみました。一旦、研究室にもってきてみんなで臭いかぎ。花と葉の部分では香りが違うんですよね。
| 5月 25日 研究の様子・樽チーム 樽材をテーマにしている学生さんの様子を見せてもらいました。焼き具合の違いで成分がどのように異なるか調べるそうです。今日は、香りの違いを調べたいということで、臭いかぎ付ガスクロマトグラフィーの練習をしていました。このところ稼働できていない分析機器なので、今年から復活したいです。
| 5月 2日 OBによるワインの勉強会 連休を利用してインポーターに就職したOBがやってきました。今回は、海外ワインの値上げとそれに伴う取り扱い商品の新規開拓などなどを調査したいということで、研究室の学生協力のもと、いくつかの国のワインをテイスティングして比較しました。こうやって頑張っている先輩の姿をみると学生も励みになりますね。ゼミの時より生き生きしていました。
| 5月 1日 OBは元気でした 連休中に研究室のOBが山梨方面にやってきたそうです。お酒関係(ウィスキー、ビール、ワイン)に就職して頑張っていること、あと農業系で頑張っているOB。元気そうにされているのが何よりです。ますますの活躍を期待しています。状況が落ち着いたら研究室合宿を兼ねてOB、OG訪問めぐりしたいですね
| 4月 27日 勉強会 今年度からの取り組み(一部ではすでにおこなっていたかもしれませんが)として、研究室ゼミとは別で勉強会を始めました。共通する研究キーワードをもっているメンバー同士で教科書や論文を読んだり発表したりするところから始めています。今のところ酸関連の勉強会と樽関係の勉強会が行われています。
| 4月 11日 写真撮影 大学広報用の写真素材をプロのカメラマンがとりに来てくれました。
| 4月 2日 研究室の様子 大学広報用の写真素材を求められることが良くあります。急ぎで実験風景素材を求められたので博士学生に協力いただき写真を撮ったのですが・・・。採用されなかったのでこちらに掲載。
| 4月 1日 研究室 始動 新メンバーになり、最初の導入実験(ワインの一般分析)が始まりました。アルコールや滴定酸度などいろいろと計測の仕方を覚えていただきます。そんな時に問題発生。分光光度計の測定用セルは石英セルとガラスセルがあり、測定波長で使い分けをします。それぞれ保管容器があるのですが、見た目では区別できないので、気づいたら中身がぐちゃぐちゃ・・・とため息交じりの准教授と博士学生さんです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||