 |
 |
 |
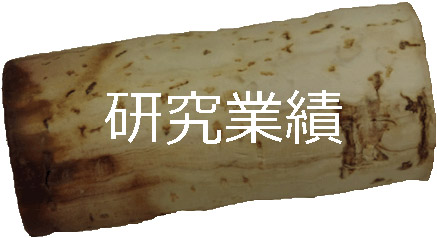 |
 |
 |
 |
 |
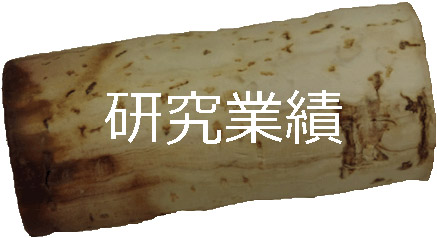 |
 |
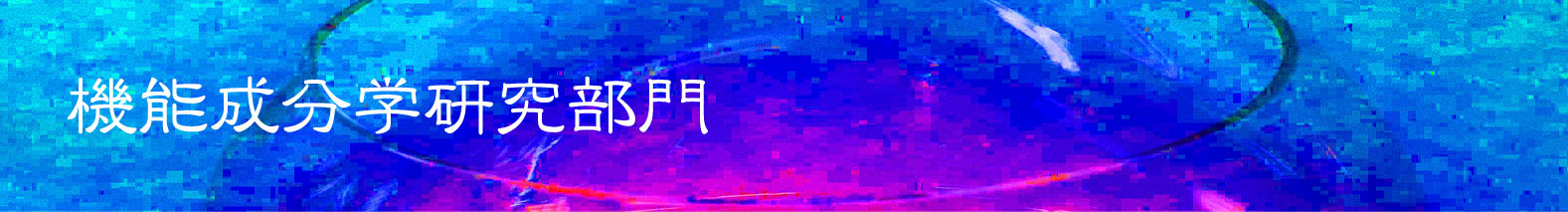
| 機能成分学研究部門で行っているゼミや実習など (作成中) |
前期ゼミ 4月〜7月頃 |
| 1.教員による導入ゼミ Word、Excelの使い方、文献検索のやり方、実験操作の基礎知識、プレゼンテーションのやり方 など |
| 2.教科書ゼミ Understanding Wine Chemistryを読みます。担当範囲をみんなにわかるように説明します。説明することで理解を深めます。 |
| 3.テーマゼミ 自分の研究テーマについて、その背景や既報、そして研究の目的と計画を説明します。卒論はつい言われたことをやる作業になりがちですが、テーマゼミをやることで、なぜこの実験をしなければならないのか?を自分自身で理解する機会になると思っています。 |
| 4.論文ゼミ 自分の研究に関連する論文をみんなにわかるように説明します。それと同時に、実験内容に問題はないか?などもみんなで議論します。 |
| 5.実験ゼミ 自分の研究の進捗状況を報告する会です。毎回、冷や汗がでます。ここで、実験の方針に問題がないか?困っていることがあればみんなでアイディアを出したり議論をする場になっています。 |
| 6.自主勉強会 関連キーワードが同じメンバーで、自主的に勉強会をしたりしています。今のところ、樽の勉強会と酸の勉強会をしています。 |
2.ワインの一般分析 3月〜4月頃 |
| 1.浮ひょう法による比重の測定 |
| 2.蒸留-密度法によるアルコール分の測定 |
| 3.エキス分の算出 |
| 4.滴定法による総酸(滴定酸度)と資化性窒素(ホルモール窒素)の測定 |
| 5.通気蒸留・滴定法(ランキン法)による亜硫酸の測定 |
| 6.可視スペクトル分析による全フェノール,全ヒドロキシシンナム酸量およびワインカラーの測定 |
| 7.色差計による色差の測定 |
| 8.ソモギ・ネルソン法による還元糖の測定 |
| 9.ホルムアルデヒド沈殿法によるフラボノイドの定量 |
| 10.フォーリン・シオカルト(F-C: Folin-Ciocalteu法)法による全フェノールの測定 |
| 11.BSA沈殿法によるプロアントシアニジンの測定 |
| 12. |
3.共通仕込み 8月〜9月頃 |
| 発酵微生物工学研究室と分担して、白ワイン(甲州、シャルドネ)、赤ワイン(マスカット・ベーリーA、カベルネ・ソーヴィニヨン)を1品種ずつ協力して醸造します |
4.学会活動(日本ブドウ・ワイン学会) 11月〜12月頃 |
| 機能成分学研究室は日本ブドウ・ワイン学会の事務局活動を行っております。その一環で、秋に大会を開催しております。大会の運営や、研究発表を行います。 |
| Copyright(c) 2013 Laboratory of Biofunctional Science, Yamanashi university, All Rights Reserved. |